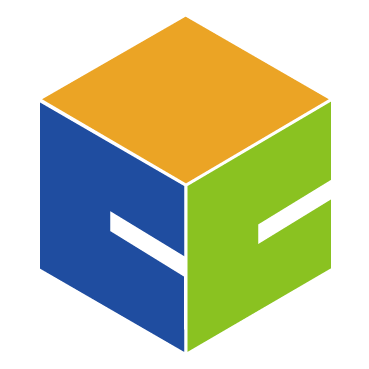連続運転時間の定義とは?法改正や超過しないためのポイントを徹底解説!

2024年4月からドライバーの安全と健康を守る「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が大きく改正されました。 この規則には、ドライバーが連続で運転できる時間は4時間までとする連続運転時間に関した規定もあり、交通事故防止と労働環境改善の両面で重要な役割を担っています。
特に今回の法改正では、今までの「休憩等」という曖昧な表現から「明確な休憩」への変更など、より厳格なルールが導入されました。 長時間の車の運転は疲れを溜めてしまい、注意力低下や判断ミスを引き起こす恐れがあるため、休憩時間の確保は物流業務の安全性向上に直結するでしょう。
本記事では、連続運転時間の上限や例外規定、休憩時間の取り方など、連続運転時間に関する基本ルールを詳しく解説します。 また、2024年4月からの法改正ポイントや関連する規制にも触れながら、物流事業者やドライバーが知っておくべき重要な情報をお伝えします。 規則遵守のための具体的な対策と共に、効率的な運行管理の方法についても考えてみましょう。
連続運転時間に関する規則「430休憩」とは?

連続運転時間に関する規則「430休憩」とは、ドライバーが4時間を超えて運転する場合、30分以上の休憩を取ることを義務付ける規則です。 「ヨンサンマル」と読み、4時間と30分を表す数字に由来しています。この休憩方法には、一度に30分の休憩を取る方法と、 おおむね連続10分以上の中断を複数回に分けて合計30分以上取る方法があります。
また、労働基準法の改正に伴い、2024年には改善基準告示および430休憩に関する規制も改正されています。 ドライバーの過労軽減と交通事故防止を主な目的とし、より安全で健康的な運送業務の実現を目指しているのです。
430休憩に関しては、こちらの記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
→430休憩とは?ルールや2024年4月からの法改正・遵守のポイントを徹底解説!
連続運転時間の定義とは?

連続運転時間とは、ドライバーが休憩や仮眠等で運転を中断することなく、継続して運転し続ける時間のことです。 運転の途中で10分程度の休憩をとった時点で、連続運転時間の更新はストップします。
01連続運転時間の上限は4時間
基本ルールとして、連続運転時間は4時間が上限と明確されています。 これは厚生労働省が定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に基づくものであり、すべてのドライバーに適用されるものです。
つまり、4時間を超えて連続して運転を行うことは原則として認められていません。 4時間という上限は、ドライバーの疲れ度合いや注意力の低下を考慮して設定されており、長時間の運転による事故リスクを減らすための基準となっています。
ドライバーは4時間の運転後、必ず30分以上の休憩をしなければなりません。 この休憩はドライバーが十分に休息を取り、疲れを回復させるための時間として位置づけられています。 休憩時間中は運転席から離れ、リラックスすることが推奨されており、運転から完全に離れることが求められます。
このような明確なルールを守ることで、ドライバー自身の健康を守るとともに、道路交通の安全性向上にも貢献できるでしょう。
02やむを得ない場合は4時間30分まで延長可能
基本的に連続運転時間は4時間までですが、やむを得ない事情がある場合に限り、最大で4時間30分まで延ばしてもいいと認められています。 この「やむを得ない場合」とは、例えば安全に停車できる場所がない、または予期せぬ渋滞が発生した場合などが該当します。 ただし、この措置はあくまでも例外的な対応であり、常態化させるべきではありません。
やむを得ない場合でも、その後にできるだけ早く安全な場所に停車し、休憩を取ることが重要です。 4時間30分を超える運転は、どのような状況であっても認められていないため、運行計画を立てる際には余裕を持ったスケジュールを組むことが求められます。
また、ドライバー自身も体調管理に気を配り、疲労を感じた場合には無理をせず、安全な場所で休憩を取るという判断が必要です。 ドライバーの安全と健康を守るためにも、この延長規定を適切に理解し、遵守することが大切です。
連続運転時間を超過したら罰則はある?

違反した場合、直接的な罰則は存在しません。なぜなら「改善基準告示」は法律ではなく、厚生労働大臣による告示であるためです。
しかし、違反した場合でも全く影響がないわけではありません。労働基準監督署から是正勧告や指導を受ける可能性があるため、遵守しなければならない重要なルールの1つです。
継続的に連続運転時間が4時間を超えてしまったり、休憩を取らせなかったりすると、 運行管理に関する規定違反として、地方運輸機関に通報される可能性があります。 場合によっては、道路運送法や貨物自動車運送事業法における規制に違反していると判断され、行政処分の対象となることも考えられます。
また、長時間の運転は労働環境の悪化を招き、ドライバーの疲労や事故のリスクを高める要因です。 仮に事故が発生した場合、企業の社会的責任が問われるだけでなく、業務改善命令や事業停止命令などの厳しい措置を受ける可能性もあります。 こうしたリスクを回避するためにも、規則を確実に守り、安全な運行管理を徹底することが求められます。
罰則がないからといって規則を軽視するのではなく、適切な運行管理を行い、ドライバーの安全と業務の安定性を確保することが重要です。
連続運転時間を超過しないようにするポイントを解説!

物流業界で働くドライバーにとって、連続運転時間の規制である「430休憩」は安全運行の要となるでしょう。 しかし、実際の業務では予期せぬ渋滞や荷物の積み下ろしの遅延など、様々な要因によって規定時間内での運行が難しくなることがあります。
そこで重要になるのが、事前の対策と社内体制の整備です。ここでは、連続運転時間を超過せずに安全かつ効率的に業務を遂行するためのポイントについて解説します。 ドライバーの安全と健康を守りながら、法令遵守を実現するための具体的な方法を見ていきましょう。
01社内の運転者が遵守すべきマニュアルの作成
連続運転時間の規制を確実に守るためには、明確で分かりやすいマニュアルの整備が効果的です。 マニュアルには具体的なルールだけでなく、休憩場所の情報や記録方法、違反した場合のリスクなども詳細に記載するとよいでしょう。
特に重要なのは、連続運転時間を記録・管理する方法の標準化です。 デジタルタコグラフやGPS機能付きの運行管理システムの活用方法、手動での記録が必要な場合の正確な記入方法などを明記します。 また、運転中に疲労を感じた際の対処法や、緊急時に連絡すべき担当者の連絡先なども含めておくと安心です。
このようなマニュアルを作成したら、定期的な研修会を開催して内容の周知徹底を図ることが大切です。 ドライバー同士で経験や対策を共有する場を設けることで、チーム全体の意識向上にもつながります。 日々の業務の中で実践しやすいマニュアル作りが、連続運転時間の遵守に役立つのです。
02柔軟性を持たせた運行計画の作成
連続運転時間を守るためには、現実的で柔軟性のある運行計画の作成が欠かせません。 計画を立てる際は、運転する時間だけでなく、休憩時間も明確に組み込むことが重要です。 特に渋滞が予想されるエリアや時間帯、荷物の積み下ろしに要する時間、天候の変化など、予測できるリスク要因を考慮した余裕のあるスケジュールを設定しましょう。
また、ドライバーごとの運転特性や経験値に合わせた計画を立てることも大切です。 無理な運行計画はドライバーに過度なプレッシャーをかけ、法令違反につながる可能性があります。
さらに、緊急事態が発生した場合の代替ルートやバックアッププランも事前に検討しておくと良いでしょう。 こうした柔軟性のある運行計画により、ドライバーは心理的な余裕を持って業務に取り組むことができ、結果として連続運転時間の超過防止につながります。
法改正による連続運転時間の変更点とは?

2024年4月の法改正により、連続運転時間に関するルールが明確化されました。 法改正後も連続運転時間4時間というルールに変更はありませんが、運転中断時の休憩の取り方や、運転を中断する際の時間に関して新たな文言が追加されています。
これにより、労働環境の改善が期待される一方で、運行スケジュールの見直しが不可欠です。ここでは、具体的な改正内容について詳しく解説します。
01運転時間について
ドライバーの運転時間は、「2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする」と定義されています。 運転時間に関しては、法改正後も変更はありません。
1日当たりの運転時間の計算は、 特定日とその前日、特定日とその翌日の平均運転時間を計算してどちらも9時間を超えなければ違反にはなりません。 2週平均に関しては、特定日から2週間のうち、1週目と2週目の平均運転時間を44時間以内にする必要があります。
02連続運転時間・運転中断について
改正前は、「連続運転時間が4時間を超えないうちに30分以上の運転の中断をとる必要がある」とされていました。 この際、運転をしていなければ休憩とみなされていたため、積み込みや荷下ろしの作業、トイレ休憩なども休憩時間に含めることができたのです。 しかし、改正後はこれらを含まない「純粋な休憩」を30分確保しなければいけません。
この変更は、ドライバーの負担軽減を目的としています。これまでは、実質的に休憩が取れていなくても「休憩等」としてカウントされてしまい、 結果的に十分な休息が取れないケースもありました。 しかし、改正後は休憩時間中に積み込みや荷下ろしなどの業務を行うことが禁止されるため、ドライバーは本来の意味での休憩を取れるようになりました。
ただし、この改正により、今までとは違った運行スケジュールの調整が不可欠です。 これまで「休憩等」として認められていた作業時間を考慮し、適切な休憩時間を確保するための運行計画を立てることが重要です。
さらに、「運転の中断はおおむね10分以上とし、10分未満の運転の中断が3回以上連続しないこととする」というルールも追記されています。 「おおむね連続10分以上」という表現は、原則として10分以上の休憩を取ることを求めつつ、 わずか10分未満の休憩でも認められる場合があることを示しています。例えば、9分の休憩を取った後に12分の休憩を取るといった形で、 全体として休憩が確保できていれば、厳密に10分以上でなくても認められる可能性が高いです。
しかし、休憩の取り方には注意が必要です。改正後のルールでは、10分未満の休憩が3回以上続くと、休憩を取ったとはみなされません。 例えば、5分、7分、6分といった短時間の休憩を複数回取るだけでは休憩時間として認められないため、必ず10分以上の休憩を1回は確保することが必要です。
この変更により、ドライバーはより柔軟な形で休憩を取ることができます。 しかし、運行計画の段階で休憩時間を確保できるよう調整しなければ、結果的に違反となる可能性もあるため注意が必要です。 運行管理者とドライバーが事前に休憩のタイミングを確認し、休憩を確保することで、安全な運行を実現することができるでしょう。
長距離輸送の場合、休憩を確実に取れる場所を事前に確認し、計画的に運行する必要があります。運行管理者とドライバーが連携し、休憩を適切に確保できるようにすることが求められます。
430休憩以外にもある!ドライバーに関連する法改正を解説!

規則改正は物流業界に大きな影響を与えていますが、それ以外にも2024年4月から適用された重要な法改正があります。 働き方改革や改善基準告示の改正により、トラックドライバーの労働環境は大きく変化しました。
ここでは、連続運転時間以外の主要な改正点について詳しく解説します。長時間労働の是正や安全な運転環境の確保に向けた取り組みを理解し、 適切に対応していくことが物流業界で働く皆さんには欠かせません。
01時間外労働の上限
2024年4月1日から、トラックドライバーの時間外労働には明確な制限が設けられました。 法律によって年間960時間までと定められたことで、長時間労働の是正が一層求められる状況となっています。 この上限規制に伴い生じる様々な課題は「2024年問題」と呼ばれ、物流業界全体が対応を迫られています。
一般的な労働者の場合、時間外労働が1ヵ月あたり45時間を超えられるのは、年間6ヵ月までです。 しかし、トラックドライバーについてはこのルールが適用されず、業界特有の事情を考慮した特例措置がとられています。
とはいえ、年間960時間の上限は厳守しなければならないため、各月の労働時間を適切に管理しながら、計画的な運行スケジュールを立てることが重要です。 この規制により、ドライバーの健康維持と安全な運行環境の確保が期待されています。
021日・1ヵ月・1年間の拘束時間
2024年4月の法改正により、拘束時間の上限が見直されました。1日の拘束時間は原則として13時間以内とされており、やむを得ない事情がある場合でも最大で15時間までです。 ただし、14時間を超える拘束は、週に2回までを目安とすることが推奨されています。
特に長距離の貨物輸送に関しては特例が設けられており、宿泊を伴う運行の場合、週2回までに限り16時間まで拘束時間を延ばすことが可能です。 また、1ヵ月あたりの拘束時間は284時間を超えない範囲とされ、年間では3,300時間以内という上限が明確に定められています。 これらの規制は、労使協定が締結されている場合を除き、すべての事業者に適用されます。
この法改正を受け、運行管理の計画性がこれまで以上に重要になってしまいました。 物流業者は、ドライバーの長時間労働を防ぐために拘束時間の適正管理を徹底し、安全で健全な労働環境を維持することが求められています。
032人以上のドライバーが乗務する場合の最大拘束時間
複数のドライバーが1台の車両に乗務するケースに関しても、改正が行われました。 従来から、1台の車両に2人以上のドライバーが乗務する際には、最大拘束時間を20時間まで延長できると規定されていました。 ただし、この適用には、車両内で身体を伸ばして休息できる設備が備わっていることが条件です。
今回の改正では、この基本的な規定に変更はないものの、より充実した休息環境が確保されている場合に適用される特例が新たに設けられました。 具体的には、車両内にベッドやそれに準じる休息設備が整っている場合、最大拘束時間を24時間まで延長できるようになりました。
この変更により、長距離輸送などにおいて、ドライバーが交代しながら運転する際の運行計画が、より柔軟に調整できます。 ただし、この特例を適用するには、適切な休息設備を確保することが求められます。ドライバーの十分な休息を確保しつつ、効率的な運行を実現するための重要な改正といえるでしょう。
04休息期間
休息期間とは、ドライバーが業務終了後から次の勤務が始まるまでの間に自由に使える時間を指します。 この休息期間に関して、2024年4月の法改正で大きな変更が加えられました。従来は最低8時間以上の継続した休息が必要とされていましたが、 改正後は原則として11時間以上の連続した休息が求められるようになり、最低でも9時間を下回ることは認められなくなりました。
この改正の目的は、ドライバーの十分な休息を確保し、疲労回復を促すことで安全運転を推進することにあります。 長時間の運転による疲労の蓄積は事故の大きな原因となるため、適切な休息時間の確保が極めて重要です。
一方で、長距離輸送の場合には特殊な事情があることも考慮され、例外規定が設けられています。 物流事業者は運行計画を策定する際、休息期間の確保を最優先とし、ドライバーの健康維持と安全運転の両立を図ることが求められるでしょう。
05分割休息
業務の都合上、連続して9時間以上の休息を確保することが困難なケースに対応するため、「分割休息」の制度が導入されています。 この制度では、一定の期間内での勤務回数の2分の1を上限として、休息時間を分割することが可能です。なお、「一定期間」とされるのは、 原則として1カ月程度までとされています。
分割休息には2つの方法があり、2回に分ける場合は、1回あたり最低3時間の休息を確保し、 合計で10時間以上の休息が必要です。一方で、3回に分ける場合は、合計12時間以上の休息を取る必要があります。
この制度を活用することで、運行スケジュールの柔軟性が向上しますが、十分な休息時間を確保するという基本的な考え方が重要視されています。 物流事業者は、業務の効率を向上させると同時に、ドライバーの休息時間の質と量を適切に管理することが求められます。 そのため、分割休息を導入する際には、ドライバーの疲労状況を十分に考慮し、適切な運用を行うことが不可欠です。
物流業務の効率化は株式会社コモンコムへ
ドライバーの連続運転時間について解説しました。基本的に4時間を超えると30分以上の休憩が義務付けられ、 2024年4月の法改正で「明確な休憩」が必要になりました。例外的に4時間30分まで延長可能ですが、違反が続くと是正勧告の対象となります。 事故リスク低減のため、企業は柔軟な運行計画やマニュアルの整備が求められます。さらに、時間外労働の上限や休息期間の確保なども強化されており、 適切な管理には運行管理システムの導入が不可欠です。
株式会社コモンコムが提供する「LOGI-Cube」は、物流業務の効率化と経営の「見える化」を実現するシステムです。
運送管理の「LOGI-Cube EXPRESS」、 倉庫管理の「LOGI-Cube STORAGE」、 輸出入管理の「LOGI-Cube PORT」など、物流業界の様々なニーズに対応したモジュールを展開しています。
法改正に伴う運行管理の複雑化に対応するためにも、LOGI-Cubeの導入をご検討ください。 安全な物流業務の継続と、効率的な経営を両立させるパートナーとして、株式会社コモンコムがサポートいたします。
詳しくはコモンコムの公式サイトまで
LOGI-Cube STORAGE(ロジキューブストレージ)